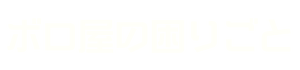みなさん、こんにちは。
築50年のボロ屋に住んでいるトモカズです。
今回の記事のテーマは「ネズミ」です。
みなさんのご自宅にはネズミが出たことはありますか?
我が家ではネズミが出たりどこかへ行ったり、また帰ってきたりと慌ただしいです。
一時期だけ静かになったなと感じて安らいでいると、数ヶ月後には屋根裏で運動会が始まります。
30年前くらいが一番ひどく、壁土に穴を開けられたこともありました。
(最初は金属タワシで穴を塞いでいました。その後はモルタル埋めました。)
ここ数年の間は壁を破ってくることはありませんが、人目につかないところでガサガサやっていることがあります。
ネズミは夜行性なので夜に活発に動き回ります。
夜のうちに捕まえられると良いなと思い、屋根裏に罠だけは仕掛けるのですが逃げられてしまっています。
ボロ屋を騒がすネズミの種類
ネズミは小さな穴があれば家の中に入ってきてしまうので、古い家ほど入ってくる可能性が上がります。
家の中に入ってくるネズミが、迷い込みネズミなら「いつかいなくなる」こともありますが、「住みついてしまった」場合は厄介です。
ねずみ算式に・・・の言葉の通り、繁殖能力がとても高く、数が増えてしまいます。
また学習能力も高いので、罠を仕掛けても逃げてしまうことがあります。
家の中に入り込んでくるネズミの種類ですが、多くは次の3種類です。
ここでは家に出るネズミの特徴や、見分けのポイントを紹介していきます。
あなたの家に出るネズミが何なのか突き止め、しっかり対策していきましょう。
ハツカネズミ
色:白色・茶色・黒色・ぶちなど個体差あり。
特徴:耳が大きく、尻尾は体長より短い。好奇心旺盛。身軽で素早い。泳ぎは苦手。
棲家:乾燥していて狭い場所が好き。自然環境に近い建物に住み着く。田舎に多い。
エサ:雑食。特に穀物が好き。野菜・果物や昆虫も食べる。
体が小さいのでわずかな隙間からでも侵入できます。
住宅(天井裏・台所)や物置小屋などに住み着きます。
冬場は特に寒さをしのぐために人間の住む家に侵入してくる傾向があります。
警戒心はそれほど高くはありませんが、動きが素早いので捕獲が大変です。
また、繁殖能力が高く、一度住み着いてしまうと駆除しきれなくなります。
ハツカネズミのフンは米粒くらいの大きさで、両端が尖った形をしています。
ドブネズミ
色:背面は赤褐色や灰褐色。お腹は白色。
特徴:耳が小さく、尻尾も体長より短い。高いところに登ることが苦手で、湿気の多いところが好き。どう猛な性格。泳ぎが得意。
棲家:台所、床下など平らな場所に住み着く。公園や排水管にも生息。
エサ:動物性のものを好んで食る。肉や魚、昆虫など。人間の食べるものはなんでも食べるので生ごみが荒らされます。
警戒心はあまり高くないため駆除は比較的簡単です。
体格が大きいので小さな隙間から直接入ることはありませんが、1cmほどの小さな穴でもかじって広げて中に入ってしまうため、自宅にある小さな穴の存在は要注意です。
ドブネズミのフンは1cmほどの大きさで、楕円形で片側の先が尖っているのが特徴です。
クマネズミ
色:背面は暗い灰色、褐色。お腹は黄色味がかかった白。
特徴:耳が大きく、胴体よりも長い尻尾を持つ。身体能力が高い。泳げるけど泳がない。壁登りが得意。
棲家:湿気の少なく高い場所。ビルや天井裏、壁の中など。
エサ:雑食。植物系のものが好き。特に穀物類。人間の食べ物は食べます。
臆病な性格で警戒心も強いため罠にかかりにくいです。そのため駆除が難しいです。
柔らかい壁はかじって穴を開けてしまうため、たとえ隙間や穴が開いていなくても注意が必要です。
クマネズミのフンは8mmほどの大きさで細長く不揃いです。あちこちに散らばっています。
ネズミの出やすいボロ屋の特徴
特徴1:エサが手に入りやすい

前項でも触れましたが、家に出没する3種類のネズミの全てが「人間の食べ物を食べる」ということです。
お米や野菜、肉や魚。
なんでも食べられてしまいます。
畑で収穫してきた野菜、田んぼで採れたお米、スーパーで買ってきた食品。
それらの食べ物のストックが、ネズミの手の届きやすいところにあるとすればアウトです。
ネズミにとってはがんばらなくてもすぐそこにエサがある環境と言えます。
特徴2:ネズミにとって住みやすい環境

ボロ屋の場合は特に色々な物が部屋の中に散乱していたり、新聞や雑誌、服なども床に散乱していることもあるでしょう。
物陰がたくさんあるということは、身を隠すのにもってこいですし、巣作りするのに必要な材料も手に入りやすいです。
冬の寒さだって凌げることでしょう。
ネズミにとっての快適な環境がボロ屋にはあります。
特徴3:家に入りやすい

ネズミにとって入りやすい侵入口があったり、ネズミ自身でかじって穴を拡大できる素材だった場合など、簡単に侵入を許してしまいます。
特に古い家には口の大きな通風口がある場合が多く、侵入は簡単です。
また木材も腐っていたり柔らかくなっていたりする場合にはかじられて穴を開けられてしまいます。
ボロ屋にネズミが出ると困ってしまうこと
ボロ屋にネズミが出るようになると、一体どのようなことに困るのでしょうか?
それらを項目ごとにまとめました。
屋根裏で足音がする
ネズミは夜行性なので、夜になると天井裏でバタバタと足音が聞こえてきます。
これから寝ようと思っていたタイミングで「バタバタバタ・・・・・」「ドタドタドタ・・・・」と音が聞こえてくると気になってしまいますよね?
神経質な方などは、安心して眠れず睡眠障害になってしまうこともあるようです。
配線や家具がかじられる

ネズミは物をかじる習性があるので、配管や電線コードなどをかじることがあります。
運が悪いとガス漏れや漏電など火災の原因となることもあります。
火事になってしまうと経済的損失・・・というか私たちが住む場所が消えてしまうのでショックが計り知れません。
また柱や壁、家具などをかじることもありますので、修理が必要になったり資産価値が下がったりするなどの被害が発生します。
人間の食糧がかじられる
人が食べる食糧はネズミも好んで食べるので、私たちの食糧を奪われます。
せっかく畑で収穫してきた食べ物を・・・。
と、しっかりと管理していないと翌朝ねずみに食べられていたなんてことはよくある話です。
お仏壇の供物なども注意が必要です。
ネズミのフンが落ちている
ネズミが住み着くと床や屋根裏に糞尿が落ちます。
悪臭にストレスを覚えたり、木材も腐食して痛みが進行してしまうので要注意です。
ダニが発生する
ネズミにはイエダニという種類のダニが寄生しています。
宿主が巣からいなくなったり死んだりしてダニが吸血できなくなると、血を求めて移動し、人を吸血するようになります。
皮膚が痒くなったり発疹を引き起こすことがあります。
ダニだけでなくノミがいることもありますので、「かゆい」と感じたら要注意です。
ウイルスがもたらされる
ネズミはさまざまな病気の原因の運び屋です。
特にネズミのフンには下記のような病原菌が潜んでいることがあります。
- 「サルモネラ菌」・・・吐き気や腹痛、高熱、下痢を引き起こす。
- 「レプトスピラ菌」・・・黄疸や出血(吐血・血便)、肝障害を引き起こす。
- 「ハンタウイルス」・・・発熱、腎不全、全身の皮膚・臓器からの出血を引き起こす。
ネズミのフンを見つけたら速やかに掃除をしましょう。
もし素手で触ってしまったら、薬用石鹸などできれいに洗い落としましょう。
ボロ屋のネズミ対策・駆除方法
まずは対策としてネズミが住みにくい環境にしておくことが大切です。
ネズミが住み着かないようにするために
- ネズミがかじりやすそうなところにエサとなるようなものを置いておかない。
- 生ごみは早めに処分する。いつまでも三角コーナーに入れておかない。もしくはフタをする。
- ペットフードを残したままにしない。
- 侵入口となりやすそうなところをガードする。
- 隠れやすい場所をつくらない(家の中を整理整頓しておく)。
- 押し入れを定期的に整理し、風通しを良くしておく。
- ネズミの巣の材料になるようなものを、ネズミの取りやすいところに置いておかない。(ティッシュ・新聞紙・タオル・布・段ボールなど)
- 仏壇に食べ物をお供えしたままにしておかない。
などです。
これらを気を付けておくだけでも随分違ってきます。
特に「エサ」が簡単に手に入らないようにするだけで、「この家には食べ物がない」と認識してくれるので次のエサ場を求めて去っていきます。
家にネズミが住み着いてしまったときの駆除方法
ネズミが家に侵入してくる前でしたら、ネズミが嫌がる成分が含まれている忌避剤も有用ですが、住み着いてしまった場合は、追い出すか捕まえるかしかありません。
【ネズミを追い出す】
ネズミを家から追い出すには「燻煙剤(くんえんざい)」や「スプレー式忌避剤」を用います。
燻煙剤は部屋中に煙を充満させる必要があるため、衣類に匂いが着いたり、家電が壊れたりする恐れもあります。
火災探知機が煙を感知してしまう恐れもありますので、気になるものには全てカバーをしておくという準備が必要です。
物であふれかえっている家などは大掛かりになることが予想されます。
スプレータイプの忌避剤は侵入口や通り道に吹きかけて寄せ付けないようにして使用します。どちらかというと追い出すというよりも侵入させないために使います。
また、超音波で追い出すという機器もあります。
燻煙剤のような準備が不要という点で手間は省けますが、超音波に慣れてしまうと効果は無くなってしまいますし、効き目に個体差もあるようです。
直接ネズミに音が届くような場所に設置することもポイントになってきます。
実際に超音波を出す機械を使ってみましたが、私の家では効果は得られませんでした。
【ネズミを捕まえる・殺す】

昔ながらの「とりもち」タイプのネズミ捕り器や、「カゴ」タイプのネズミ捕り器は現代においてもマストな商品です。
何十年も変わらずに受け継がれてきています。
だた、こちらの罠も捕獲率が100%という訳ではなく、賢いネズミは近寄ってきてはくれません。
分かりにくいように仕掛けたり、食べたくなるようなエサを置いたりなど工夫も必要になってきます。
「殺鼠剤(さっそざい)」は、ネズミに食べさせて殺すためのいわば毒エサです。
一回食べただけで死んでしまうタイプの強い薬剤のものと、複数回に分けて食べさせて殺す弱い薬剤のものとあります。
ただし、小さなお子さんやペットがいるご家庭では事故につながることもあるため、取り扱いには注意が必要です。
【プロへ頼む】
![]() 自分ではどうしてもネズミを駆除することができない。
自分ではどうしてもネズミを駆除することができない。
増え過ぎてしまって手に負えない。
など、もうどうしていいかわからないくらいまでになっているのならプロに頼んでしまうのがよいでしょう。
<PR>
![]()
業者によってはネズミの処理だけでなく、ネズミの糞尿や菌で汚れた場所の掃除も行ってもらえたり、再発予防のために手を施して頂けたりなど、確実にネズミを退治しやすくなります。
まとめ
今回の記事では家に住みつくネズミの種類や困りごと、その対策に至るまでをまとめました。
ネズミが住みついてしまうことで起きる数々の問題の中でもウイルスや菌に脅かされてしまうことになったら恐ろしいなと思います。
現状、我が家では住みついていたり増えている感じはないので、かろうじて安心しています。
食糧も荒らされてはいませんので、守り切れていると思います。
ですが、たまにやってきて屋根裏でドタバタやっているのだけはいただけません。
今後も適宜対策をしていきたいと思います。
みなさまも、もしネズミの気配を感じておられましたらお気を付けくださいね。